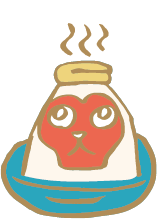この遺跡は、縄文時代中期の配石遺構群を伴う、縄文時代前期末から後期にかけての集落跡です。
特に、配石遺構と呼ばれる石組み群が、丘陵西側の緩い斜面部から平坦部にかけての一帯に不規則に分布し、石を組んだモニュメントが37個発見され有名になりました。
東側の高台上には約5,000年前の村が、西側の斜面には約4,000年前の村があり、モニュメントの造られた時期は謎の一つです。
個々の石組みの石の並べ方にいくつかの型が認められますが、花崗岩(かこうがん)の細長い川原石1個を立てた周りに、数個の山石を放射状に並べたものを典型とします。
石組みの下は少しくぼんでいますが、土こう(あな)と言えるものではありません。
石組みに伴って出土した土器や石器から縄文時代中期のものと考えられます。
配石遺構は、縄文時代前期から知られていましたが、樺山遺跡以降の代表的なものとして、秋田県鹿角市の大湯環状列石があります。
これは縄文時代後期のもので、石組み群の中の日時計と呼ばれているものが、樺山遺跡の石組みに似ており、樺山遺跡のものを祖源とみることができます。
このような配石遺構は何のために造られたかについては、以前から墓地とみる説と、祭り場とみる説とがありますが、北海道地方では墓地がほとんどであり、その他の地方では両者があって一様ではありません。樺山遺跡では、墓であるかどうかをみるため、石組みの下の土を 「リン分」 の分析しましたが、墓としての確かな証拠が得られませんでした。
丘陵上には、配石遺構を造った人々が生活した場所と考えられ、縄文時代中期の竪穴式住居が復元されており、史跡公園として親しまれています。

・樺山歴史の広場

・竪穴式住居(復元)

・樺山歴史の広場
https://kitakami-kanko.jp/location/kabayama/